節約したいので、家計簿つけようかなーと言う人は多いですよね。
昔は「電卓をつかった手書きの家計簿」が一択でした。今ではパソコンやアプリなど、いろいろなタイプが販売されています。
「どれも、とっても便利そう。でも、初心者でも続けられるのはどれ?」
私も家計簿選びすごーく悩みました。そこで今回は、初心やでも続くのは手書きとパソコンどっちか、メリットをまとめましたので紹介しますね。
後半、初心者でも簡単につけられる家計簿を紹介しています。実際に使ってみた感想もあわせて掲載していますので、興味のある方は是非参考になさってくださいね!
スポンサーリンク
家計簿は手書きとパソコンどっちがメリットが多い?
まず家計簿定番なのは「手書き VS パソコン」ですね。実際、私、手書きの家計簿もパソコンも両方やってみましたが、それぞれメリットはありました。
私の感じたそれぞれ家計簿のメリットは以下の通りです(^^♪
家計簿の手書きのメリット
- 費用がかからない
- 思い立ったときにすぐかける
- アレンジがしやすい
- 家計簿をつける習慣が身につく
- 基本的な考え方を身につけやすい
- 手書きで書くだけで節約効果がある
家計簿は100円均一でも買えますし、ノートでもOK。こった形式だと千円以上しますが、最初は安いものでも全然大丈夫ですよ。費用がかからないのがいいですね。
「今日から頑張るぞー!」と思って、購入してからすぐ家計簿記入ができるのもメリットです。
あと、パソコンと比較して手軽さは断然、手書き家計簿です。さっと家計簿を開いて記入するだけ。簡単な様式なら1行かいて終わりですよ。
私の友人は手書き家計簿派。パソコンの家計簿ソフトを購入しても、起動するのが面倒になってしまい使わなくなってしまったそうです。
「結局、100円均一の家計簿つかってるよ!」といってました。住宅ローンも完済、新車でアルファードも購入していて、私からみるとかなりのやり手です。100円均一の家計簿でも十分家計をコントロールできると彼女で確信しました。
彼女曰く「手書きでささっとコメント添えられるのがいいね」と。
これは実際に家計簿をつけてみるとわかりますが、覚え書きって結構重要です。セール時期に購入した、とか。そういう、ちょっとしたお値打ち情報です。家計簿を見直した時に「ああ、この時、だから安く買えたんだ」というような、添えコメントがあると次年度以降の節約の参考になりますよー。
あとは、簡単な書式の家計簿を選べば1行かくだけなんで「毎日家計簿を書く」習慣が身につきます。難しいと初心者の人や、私のようにずぼらな性格だと、最初から難しいと続かないです。「家計簿をつける」習慣を身につけるという点でも手書きはおすすめ。
手書きは「いつ、何を買ったのか」の振り返りになるので、 レコーディングダイエットのように、「あー、つかっちゃったなー」とちょっとした反省にもなりますよ。
先ほどとは別の友人なんですが、「ただ、ただノートの使ったものだけ値段を書き写す」という家計簿の付け方をしている人がいて、「不思議~と節約になるよー」と言っていましたよ。
家計簿パソコンのメリット
- 集計をとらなくてもすむ
- できあがりの精度が高い
- 分析がしやすい
一番のメリットは「集計」ですよね(^_^;
電卓で計算するのが苦手だと、手書き家計簿はちょっと苦しいです。その点、パソコンの場合は集計は自動なので便利ですねー。
また、パソコン派の人は
・エクセルなどの表で管理をする
・家計簿ソフトを使う
と大きく2派にわかれています。エクセルなど表計算ソフトなど自分でつくって管理しやすくしたり、あと無料でダウンロードしたり。「自分でパソコンが使える環境がある人」なら時短になりますよ。
これまた、私の家計簿ソフト推しの友人は「入力さえきちんとすれば、どこで、何を購入したら安いのか、底値もわかるよ」といっていて!!!確かに、分析するなら「家計簿ソフトの方が便利かなー」と思いました。
手書きの場合は、自分で考えないといけないですものね。
ソフトなら、ある程度、世の中全般のニーズを踏まえて作ってあるので、ポチッとボタンを押せば、いろいろな角度で「節約の提案」や「節約に役立つ情報」が楽に手に入ります。パソコンソフトだと、次の行動がとりやすいですね。
家計簿パソコンもデメリットがあります
すっごく便利そうなんですが、実はパソコン管理もデメリットがあって、
- 「旦那さんと兼用で使っていて、自分の使いたいときにパソコンが使えない」
- 「ちょっとパソコンのスペックが・・・・」
- 「エクセルなどのソフトが入っていない」
と言う方は、パソコン管理が面倒になっちゃうかもしれません。
あとは、
- パソコンを立ち上げるのが面倒
- ソフトの使い方を身につけないといけない
- 操作方法がわかりにくい
- お金の仕組みがわかりにくい
というのもデメリットかも。実際、私はパソコン立ち上げるのが面倒になって、手書きにもどしちゃったんですよ。
あと操作方法や積極的にソフトや機能を覚えていかないと宝の持ち腐れに。
逆に、初心者の人だと、至れり尽くせりなので、実際に自分の頭で「お金の流れ」を考える力がつきにくいっていうのもデメリットかなーと思います。
家計簿が手書き OR パソコン ずぼらや初心者でも続くのは?
個人的に初心者におすすめなのは「手書き」です。理由は「費用」がかからないからです。基本的な考え方を身につけることができますしね。
スポンサーリンク
「やれそうだ」と感じたら、ちょっと投資をして家計簿ソフトを買うのもいいかもしれません。家計簿は手書きだけど、集計だけはエクセルなどでする人も大勢いますよ。
私も、普段の家計簿は手書きですが、年に1度の収支表はエクセルの表に入力をして保管をしています。
まずは、初心者の人は段階を踏んで「これなら続けそうだ!」という家計簿を選んでくださいねー。
ちなみに家計簿のずぼらな人や初心者でも続けられる家計簿のおすすめは
↓いままで私が試した家計簿では、これが一番簡単でした。「かんたん家計簿」です。見開きで1ヶ月使います。
|
|
私は手書きの家計簿の使い方
こちら、私が実際につかっていた「かんたん家計簿」の「白紙」の部分です。
↓中身見えますかね? 行が「日」列が項目です。一日たった1行書くだけ。

項目は自分で自由に設定できます。
私は項目設定として
- 食費
- 日用品費
- 医療費
- 特別費
- その他
にしました。家計簿で占める割合が多い項目を4つ分類項目に設定し、あてはまらないものを「その他」にいれて、横にコメントを添えるという使い方をしていましたよ。
あと、食費もマーカーで「外食」「お菓子」など色分けしたり、かっこがきにしてみたり工夫をしていました。予算を超えなかった時に花丸をつけたり!
シールやスタンプなど使えば、かいてて楽しいのは手書きかなーと思います。
100円均一の家計簿も初心者にはおすすめです
↓ちなみにこれがダイソーの家計簿。今年は4種類ありました。全部中身の様式が違っていますよ。
書きやすさという点では、先ほど紹介した「かんたん家計簿」のが簡単です。1日1行ですからね!100円均一の家計簿は「もう少し詳しく管理したい人」「家計簿にある程度 書き慣れた人むけ」かなーという印象です。
お値段相応・以上には活躍してくれると思うのでチャレンジしてみてもいいかもしれません。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
主婦仲間でも家計簿に関する考え方って人それぞれで。
友人・知人の話を聞いてみると、家計管理をしっかりやりたいという人は、意外に自由度の高い「自分で書き込みができたり」「自分で使いやすいようにアレンジできる」タイプのものを好む気がします。
面倒は省いて、ささっと結果だけ知りたいという人はソフトかなー。
あと、そもそも「家計簿つける、つけないで夫とけんかになる」「いつも夫婦げんかのネタは家計簿」という友人もいました(^_^;
向き不向きもありますので、まずはあまり費用がかからず簡単に取り組めるタイプからチャレンジしてみて、難易度をあげていくのがベターかなーと思います。
まずは、家計簿を続けるためには、簡単にかけそうな様式・書式のものを選ぶというのコツ・鉄則ですよー。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17e4cb0c.07bd9f15.17e4cb0d.bf7ba658/?me_id=1241849&item_id=10060913&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-youstyle%2Fcabinet%2Fmidori%2Fmdr12355006_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-youstyle%2Fcabinet%2Fmidori%2Fmdr12355006_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


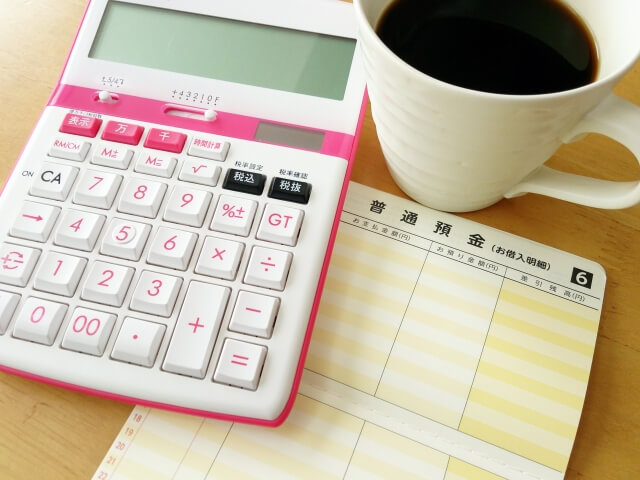
コメント